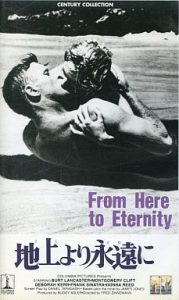
もう何十年も前の作品ながら、未だに名作として名を馳せる映画です。
軍隊の腐敗をテーマにした作品かと思いきや、男達の矜恃やほろ苦い結末まで見事に描き出してくれました。
しかし、切ないロマンスなのは確かですが、この結末にどこか納得がいかないと言うか、心の中での“おさまりが悪い”と感じた方はいなかったでしょうか?
主人公達に感情移入するほど、「なんでこんな選択を…」という思いが捨てきれないのです。
時代のせいと言えばそうかもしれませんし、ハッピーエンドを求め過ぎと言われるかも知れません。
それでも、もっと違う道があったんじゃないかと思ってしまうのです。
その収まりの悪さには理由があります。
それは、アメリカ人の心の奥底にある、どこか矛盾した“正義”が関係していました。
そしてまた、その矛盾こそが、この映画を名作に昇華する鍵でもあったのです…。
原作小説との違い
まず、この物語の核心に迫るために、原作をみてみましょう。
この映画の原作はアメリカで大ヒットした長編小説“From Here to Eternity”です。
(日本では『地上より永遠に』のタイトルで出版されています)
ところがこの小説、暴力シーンもあるわ、放送禁止用語を連呼するわ、猥褻なシーンもあるわでなかなかに過激でして…。
何年も米国の図書館で禁止されていたくらいです。(今では“名作小説100”として米国連邦議会図書館に登録されるんだから、面白いですね)
巷ではこの作品に対し“From Here to Obscenity”なんてあだ名(?)までつけられました。Obscenityは「卑猥、猥褻」って意味です(^^;
そんなヤバめの問題児な小説ですから、映画化自体が「非常に困難ていうかムリ」と思われていました。
そこをなんとか実現にこぎつけたわけですが、主なところでもこれだけの変更が加えられました。
ロリーンの職業
映画の中では「お酒も無し、ダンスと会話だけを楽しむ紳士の社交場」である会員制ソーシャルクラブの店員として描かれていましたが、原作ではもっと露骨に売春婦としています。
もっとも、映画の中にも「1年も頑張れば故郷に家が建てれる」なんてセリフもあるので、「露骨には言わないけど、察してね」ということなのかもしれませんが。(カフェの店員が1年で家を建てられるわけないですもんね~)
カレン・ホームズの不妊の理由
映画の中では、「ホームズ中隊長が医者を呼び忘れて不倫してて、死産になって…」と語られていました。
原作では「不倫をしたホームズが浮気相手から淋病をもらい、それを妻にうつしてしまい、その結果子宮を摘出する羽目になり不妊となった」というものです。
どっちにしろひどいけど、原作のほうがより生々しくて、生理的に嫌悪感が…。
主に性行為でのみ感染する性病で、女性では不妊症や子宮炎の原因になりうる。1回の性行為による感染率は約30%と高い。
未だに日本でも若年層を中心に流行っていたりする。
同性愛者の存在
原作では軍隊内に同性愛者が存在し、入隊した男性の何人かが彼と親交を結ぶ描写がありました。
またこのエピソードの結果として、1人の兵士が自殺に追い込まれています。
映画ではそのような描写は一切抹消されています。
営倉の看守長の暴力
主人公の友人アンジェロ・マジオは、営倉で看守長ジャドソン(ピアノ弾いてたデブ)から過酷な暴力を受けました。(※営倉とは、軍隊内にある、規律違反の隊員を処罰するための牢屋みたいなものです)
原作では、看守長だけでなく営倉の看守達が組織ぐるみで彼に暴力をふるっていたことが描写されています。
一方、映画では看守長ジャドソン(ピアノ弾いてたデブ)について「あいつはサディスティックな性格だから気をつけろ」とのセリフがあるように、ジャドソンの性格が異常であり彼一人だけの暴走であることが強調されています。
なお、映画では「マジオが酷い暴力受けていたよ」と伝聞で事実を知りましたが、原作では虐待の描写が生々しく描かれていたりします。
アンジェロ・マジオの死因
映画ではマジオの死因について、車で脱出する際に道路に落ちたことが直接の死因(あるいは虐待で弱った身体への最後のダメ押し)のように描かれています。
ところが小説では、そもそもそんなシーンがありません。マジオは看守達の暴力のみで死に至ったのです。
ホームズ中隊長の末路
映画ではホームズ中隊長は軍上層部に圧力をかけられ、軍法会議にかけられる前に辞職しました。「解雇」じゃなくて「自主的な退職」にしてもらう、みたいなものでしょう。
軍法会議で不名誉な判決を受け、今後の就職活動や名声などに影響がでることを避ける意味もありますが、軍自体の醜聞を隠蔽する意味合いもあると言えます。
完全勝利とは言い難いですが、一応は正義の勝利と言えるでしょう。
一方、原作小説では、なんとホームズ中隊長は昇進していったのです。軍法会議も内々の処罰もありませんでした。まったくもって救いがありません。
なぜ原作から変更されたのか①
ひとつは、この公開当時の映画業界には、今よりもずっと厳しい規制“プロダクションコード”があったせいです。
もともとは、1930年代にギャング映画が台頭し始め、暴力を美化するのをやめようという政治的な運動からMPAA(アメリカ映画製作配給業者協会)により運用されたものでした。
しかしその規制内容は
宗教の冒涜、殺人や犯行の細部を描く、中絶、同性愛、薬物、売春、強姦、白人と黒人が交わること、出産、ヌード、性的な抱擁、卑猥な言葉、口を開けたキス
と、かなり行きすぎたもの。
だからこの映画では売春婦や同性愛や暴力を描けなかったし、カレン・ホームズの不妊の理由をマイルドにする必要がありました。
また、プルーイットが看守長ジャドソンを刺殺するシーンでも、“揉み合いながら物陰に移動し、出てきた時には刺されている”という苦しい手法で表現しています。これも、緊張感を持たせるために婉曲な表現をしたとかではなくて、直接的な犯行描写を避けるための処置です。
なぜ原作から変更されたのか②
この映画が原作から変更されたのにはもう一つ理由があります。そして、こちらのほうがより重要な意味を持っています。
原作小説と映画で変更された点を改めてみてみると
…要するに、原作小説では映画に輪を掛けて「軍の内部はクソである」と強調しているのです。
ところがこの映画、制作に当たって米軍の協力を得ています。
実際の真珠湾攻撃時の映像を使用したり、撮影において米軍の基地や装備をお借りする必要があったのです。
もちろん、米軍としては「軍の内部はクソである」と声高に叫ぶ映画を応援したいはずもありません。
しかし、プロデューサーのバディ・アドラーが元・米軍中佐だった縁もあり、“一定の検閲をする”という条件で協力をすることになりました。(原作小説と映画を切り離そうとタイトルの変更も求めましたが、それは制作会社のコロンビアピクチャーが断固拒否しました。)
その“一定の検閲”の結果、原作と比べて随分マイルドといいますか、米軍のヒドさを描ききれない映画になってしまったのです。(特に看守の暴力や、ホームズ中隊長の進退については軍の指示により変更されました)
原作小説の著者ジェームス・ジョーンズはお上品になってしまった映画版に不満を抱いていました。
また、映画で監督を務めたフレッド・ジンネマンもホームズ中隊長の進退に関する描写が変更を余儀なくされた件について「この映画の最悪の瞬間だ、観る度に気持ち悪くなる」と述べています。
一方でアメリカ軍も、完成した映画の描写に満足しておらず、オープニングクレジットにアメリカ陸軍の名前が載ることを拒否しました。
アメリカの事情
原作小説の大ヒット、アメリカ軍の拒否反応。
この一連の流れで透けて見えてくるのが、アメリカ国民の間に広がる軍への潜在的な嫌悪感と、それを危惧するアメリカ軍の苛立ちです。
当時アメリカは、国民を強制的に軍隊入りさせる徴兵制を採用していました。
しかも、動員される人数が今とは比べものになりません。
第二次世界大戦中の1945年は1,205万人もの将兵が動員されていました。これは就業人口に対する比率で18.6%にものぼります。働く人間の5人に1人!
動員される多くが若い男性だったことを考えると、若い男性はかなりの割合で軍に入ることを強制されていました。
つまり、大戦中の日本と同じような「国家総動員」っぷりだったわけです。
(なお2006年のアメリカ軍の将兵は144万人。就業人口に対する比率は1.0%にすぎず、全てが志願兵で構成されています)
ところがちょいと複雑なことに、アメリカは戦争に勝っちゃいました。
戦争に負けた日本は「戦争は間違いであった」「徴兵され死んでいった若者は哀れだ」「二度と繰り返してはならない」という意識が国民の間に強く広がりました。
一方、勝利したアメリカでは、「戦争」も「徴兵」も、あるいは「軍の中の腐敗」までもが正当化されてしまったのです。
結局勝てたのは誰のおかげだ?軍さ!YEAH!
それでも、言いづらかっただけで、多くの国民が軍の中で腐敗を目の当たりにしていたのは事実です。
社会に戻った従軍経験者を中心に、国民の間に「軍の内部はクソである」という意識が、ひっそりと、しかし確実に浸透していきます。
やがてそれが、軍の内部を赤裸々に描いた原作小説の大ヒットに繋がります。
軍への批判が潜在的に高まっていくことを肌で感じ、さぞや軍司令部はやきもきしたことでしょう。
軍への複雑な気持ち
しかしアメリカ人を外からみると、どうも「軍を嫌悪する気持ち」だけでなくて、逆の気持ちが同時に存在しているような気がしてならないのです。(それこそが冒頭の「おさまりの悪さ」に繋がります)
少し話が外れますが、知人がハワイで体験したちょっとしたエピソードを紹介します。
ハワイに滞在中のあるコンサートで、出演したアーティストが「この中に軍人、あるいは元・軍人の方はいらっしゃいますか?」と問いかけました。
すると観客のうち何人かが起立し、アーティストだけでなく他の観客からも、彼らに惜しみない拍手が向けられました。
その後、彼らに捧げる歌が演奏される間、バックのスクリーンには米軍兵士の勇姿がスライドショーで延々と流れていたそうです。
知人は「みんなが一丸となって兵士をストレートに賞賛する姿勢や、それに違和感を感じない観客達にカルチャーショックを受けた」と言っていました。
たしかに、日本ではなかなかお目にかかれない光景です。
また、インターネットで海外のおもしろ動画や感動動画をフォローしていると、感動系の鉄板ネタとして『軍から一時帰宅するお父さんと出迎える子どもの様子』動画が非常に多い事に気づかされます。
もちろん子どもの思わぬリアクションやハイテンションなはしゃぎっぷりが主な人気なのでしょうが、ここでもアメリカ国内での「軍から一時帰宅するお父さん」への潜在的な敬意が感じられます。
真珠湾攻撃が始まるや否や、ウォーデン曹長は有能な指揮官として立ち上がり、プルーイットは危険を覚悟で軍の元へ馳せ参じました。
なぜ、軍をボロクソに描く一方で、“軍に身を捧げる男達”をあんなに魅力的に描いたのでしょう?
どうやらアメリカ人の中では、“軍を嫌悪する気持ち”と“軍に身を捧げる男達を愛する気持ち”が同時に存在しているようなのです。
あるいは、「軍という組織は批判されるべきだが、兵士ひとりひとりは尊い」ということなのでしょうか。
第二次世界大戦で勝利したからこそなのか、それとも愛国心の問題なのでしょうか。
若い人は覚えているかわかりませんが、9.11テロ事件の後には「U・S・A!U・S・A!」と気勢を上げるアメリカ人の姿がテレビで何度も流されていました。
アメリカ人の愛国心はスゴイ、と強烈な印象で覚えています。
相反する二つの正義
一方、アメリカは言わずと知れた個人主義の国です。
個人主義を辞書で引くと
- 個人の意義・価値を強調し、個人の自由・独立を尊重する立場
- 俗に、利己主義のこと
と出てきます。
これって、思いっきり徴兵制や軍隊内の腐敗と相反しています。
アメリカ人がそのことに気づいていないとは考えられません。
おそらく、個人主義を重んじると誇らしげに宣言しつつ、軍隊だけはアメリカ人にとって“批判すべきではない聖域”だったのでしょう。
アメリカでは、軍隊と個人主義という相反する二つの正義が矛盾しながら両立していたのです。
もちろんアメリカ人の中でも、この矛盾への葛藤があったのかもしれません。
そんな中この映画では「軍隊は腐敗しており、個人主義とは相反する」と一定の批判をした上で、矛盾への秀逸な回答を用意していたんです。
それは、一匹狼を貫き最後は軍に身を捧げようと散っていったプルーイットを通して表現した、『個人主義を貫いた上での滅私愛国』です。
軍と個人主義、二つの正義のどちらにも敬意を払った美しい結論ですね。
それに、どこか男のロマンを感じさせるカッコイイ響きじゃないですか、『個人主義を貫いた上での滅私愛国』って(笑)
アメリカの男達も、この答えには大きく頷き納得したのではないでしょうか。
そしてもうひとつ、この映画をもっともっと面白くしているのは「それでもやっぱり納得できない女性二人」を描いたた点です。
『個人主義を貫いた上での滅私愛国』はカッコよく、完璧な答にも思えます。
でもそれは、美しく散っていけば本望の“男の論理”でしかありません。
残される女性にとっては、決して心から納得できる答えではないのです。
あのわずかなラストシーンがなければ、男がうっとりするような“かっこいい一人の兵隊の映画”にすぎません。
戦争に行く男と、見送る女。その間には決して埋められない溝があると痛感させられます。
短くても、強烈な印象を残したシーンでした。
まとめ
この映画の魅力は往年の名優の競演だけではありません。
相反する二つの正義。軍隊への敬意と個人主義。そして男と女。
アメリカに横たわる葛藤が多くの人の心を深く揺さぶったからこそ、名作なんですね。



















































