なぜこの映画が名作と評価されたのか。それには当時の時代背景が大きく関係しています。
現代に生きる私たちには、予備知識なしにこの映画の切なさを理解し、共感するのは少し難しいのです。
一人の男の生き様
この映画を一言でいうなら“一人の男の人生”そのものだと言えます。
成功もしたし、失敗もしました。
いつも真剣に挑戦し続け、何かを掴もうと必死になって
まっすぐで不器用なまさに“男”。
ジェイク・ラモッタは実在のボクサー元世界チャンピオンで、
レイジング・ブル(怒れる雄牛)というニックネームで知られていました。

彼のボクシングスタイルはそのまんま“ブルファイター”と呼ばれるものでした。
相手のパンチ器用に避けたりは出来ないけれど、
打たれても打たれても愚直に前にでるスタイルです。
どんなに相手が強くても、傷だらけになっても、一歩も引かずにひたすら前へ。
そして目の前の敵をひたすら殴りつける!!
泥臭く、不器用で、それゆえに観るものの心をひきつける熱いスタイルです。
ジェイク・ラモッタの生き様そのものにも、同じことが言えます。
実は彼は、(家族への専横な態度を別にすれば)悪事らしい悪事はしていないんです。
チャンピオンの座から落ちてしまったのも、残念だけれど仕方ありません。
引退するまでチャンピオンで居続けた人なんて、世界中でほんの一握りでしょう。
刑務所に収監されてしまった事件も、不注意ではありましたが悪意はなかったのです。
八百長に乗ってしまったのは確かに悪事ですが…
あれはチャンピオンへの挑戦権を得るための取引でした。
少しばかり大目に見てあげたい気持ちです。
中年太りになってしまったのは、たしかに見苦しいですが、
もはや悪事でも何でもありません(笑)
目標に向かって突き進むうちにボロボロになってしまった彼を観ていて、切なくて、どこか憎めないと思うかもしれません。
それはきっと、我々男性が同じくらい不器用だからです。
その不器用さに同情し、共感してしまうからなのでしょう。
そんな彼の人生を、ただ黙々と映し続けて幕を閉じる…
この映画はただ「一人の男の人生」なのです。
賞賛か、批判か
彼の人生に対する明確なメッセージは少なく、その判断は観客にゆだねられているようにも思えます。
賞賛とまではいかなくても、たしかに求道士のような生き様にはある種のロマンを感じるのは確かでしょう。
映画冒頭の、雪の降る冷たいリングでガウンをかぶってシャドーを繰り返す描写が印象的でした。
改めてこのシーンを見直すと、まさに主人公の生き様のような素敵なカットです。
不器用で報われない努力家である彼には、同情や共感だって感じられるでしょう。
しかし、明確な批判の台詞はなくても、映画が伝えたかったことは明白です。
この映画は、彼の生き様を賞賛なんてしていません。
あえて批判をおそれず断言しましょう、
彼の人生は“失敗”だったのです。
彼は最後になにも掴んでいないのです。
裕福でもなく、親しい人もおらず、自分に言い聞かせないと自信すらも保てません。
結局彼は不十分だったのです。
あれだけの犠牲を払い、チャンピオンにまでなったというのに。
足りなかったものは何でしょうか。
彼の手からすり抜けていったものは何でしょうか。
奥さん、家族、兄弟…
そう、家族です。家族なのです。
チャンピオンであり続けることでもないし、
裕福な生活でもありません。
社会的な「成功」があったって、
家族がいなければダメなのです。
主人公が仮にチャンピオンになれなかったとしても、
今よりずっと慎ましい生活をしていたとしても、
家族で仲良く食事をしているラストシーンだったら、それはハッピーエンドなんじゃないでしょうか。
彼には“見えていなかった”のです、
家族を大切にすることがどれだけ大切なのか。
才能もあり、努力も重ねただろう彼に決定的に足りなかったもの、
それが家族を大切にすることでした。
もちろん愛していたでしょう。
この上なく愛していたのでしょう。
しかしそれだけでは不十分です。
大切に思うだけではなく、行動が伴わなければいけないのです。
前の妻も、ビッキーも、弟も、
彼は誰も大切にしてきませんでした。
たしかに何度も愛しているとキスをし、ハグをしました。
でもそれだけでした。
彼は愛を表明する以上のことをなにもしなかったのです。
ラストシーン、彼は自分に言い聞かせ続けました。
I’m da boss.
I’m da boss.
I’m da boss.
ここに彼の過ちが浮きでています。
彼が自分に言い聞かせたのは “I can do it.”(俺は出来る)でも “I am talented.”(私には才能がある)でもありません。
I’m da boss.(俺はボスだ)
※da は the の代わりにスラング的に使う冠詞。参考リンク
彼はどこまでも自分がボスであろうとしました。
他人の上に立つことばかりを考え、敬意を払ってきませんでした。
偉いのは自分、正しいのは自分。
そして家族にもそんな関係を強要してしまったのです。
主人公は「奥さんに敬意と感謝を持って接する」という当たり前のことすらしてきませんでした。
だからこそ彼は本当の意味で幸せを掴めなかったのです。
哀れな男です。
しかし、理解しがたいかも知れませんが、そんな哀れさこそが“共感”を呼んだのです。
一体どういうことでしょうか?
そこで重要なのが、この映画が公開された1980年という時代背景です。
1980年という時代
実は1980年とは、アメリカ合衆国において離婚率が史上最高まで上昇した年です。
ただでさえアメリカは離婚が多いイメージがありますが、1980年当時は本当に増えていました。
下のグラフで1960年から比較してみると、急激に上昇し、2倍以上に激増していることがわかります。
(ちなみに下の方の黒い太線が日本です)
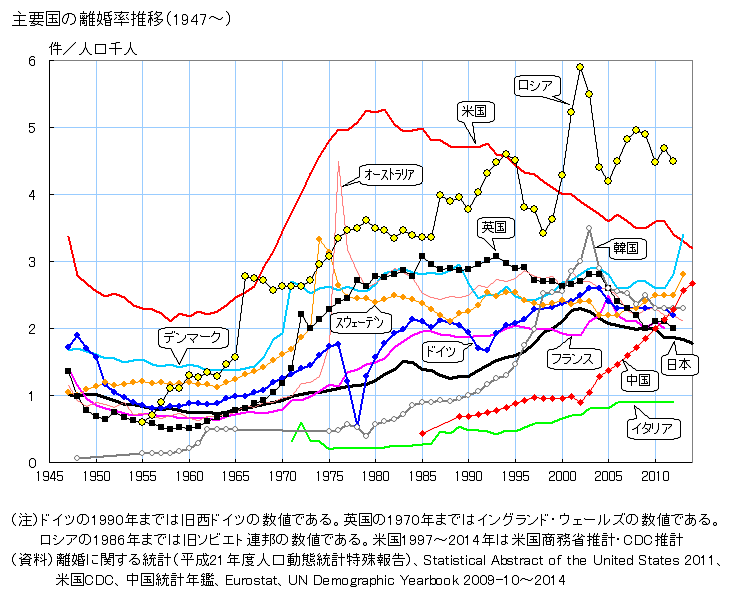
社会実像データ図録より引用
なぜ離婚率が上昇したか、一言で語るのは難しいです。
しかし、大きく影響したのは、この二つの要因といわれています。
●女性の経済的自立
●伝統的価値観の変化
言い換えれば
女性の社会進出が進み、自分自身で収入を得られるようになり
なおかつ“女性は男性に付き従い、夫婦は離婚してはいけない”という古い価値観が崩れてきたということです
逆に言えば、それまでの女性は我慢していたのでしょう。
「離婚したくても今後生活のことを考えると無理」
「周囲の目を考えると無理」
「女なんだから我慢しなきゃ」
でも、とうとう気づいたのです、女だからって我慢する必要がないのだと。
一方の男性はといえば、あいも変わらず“男らしさ”に夢中になっていました。
1950年代~1960年代には西部劇ブームが巻き起こります。
西部劇の主人公って、かっこいいですよね。
媚びない。
折れない。
自分を貫け!
そんなステレオタイプな“男らしい”生き様に心酔し、喝采を送っていたのです。
そして、家の中でもそうでした。
古い時代の家庭では父親・夫が絶対的な存在として振る舞い、それが許されていました。
「俺のいうことを聞けないのか」なんてセリフが平気で飛び出したものです。
ところが、時代は女性の権利を尊重する方向に動いていました。
もはや女性たちは、夫の横暴に我慢しなくなったのです。
1960年~70年代の西部劇ブームで育った男性達は
新しい家族のあり方に対応しようともせず、古い時代の父親のように振る舞ってきました。
そして、次々と妻から三行半を突きつけられたのでしょう。
それが、1980年という時代でした。
こんな時代背景を考えると、この映画の意味合いが少し変わってきます。
彼らも主人公と同じなんです。
家の外では仕事に励み、
家の中では厳格に振る舞い、
妻を愛していたつもりでした。
古い父親像を忠実に務めていたつもりだったのです。
それなのに、「いつのまにか家庭で居場所を失っていた」と感じていたのです。
たしかに今の時代に生きる我々からみれば、横暴に振る舞う夫の自業自得です。
しかし当時の男性にしてみれば、古き良き価値観に従ったつもりだったのでしょう。
余りに急激な時代の変化に対応できなかったのです。
彼らは戸惑い、怒り、嘆きました。
そして初めて“大切なもの”がなんだったか気づいたのです。
ロバート・デニーロはただ忠実に人物を再現するためだけに、あれだけの中年太りを再現したわけではないでしょう。
あれは、当時の中年男性が自己投影しやすくする仕掛けなのです。
いつのまにかでっぷりと太ってしまった主人公。
若い頃の魅力を失ってしまった主人公。
家族とうまくいっていない主人公。
まるで、自分のようだと。
1980年代の男性は、主人公の哀れさに“共感”していたのです。
現代の人からみれば、単に横暴で、自己中心的で、哀れな男にみえてしまうでしょう。
でも40年前は、彼のような男は決して珍しくありませんでした。
「全ての男性に通じる心情」といっても過言ではなかったかもしれないのです。
同時に、現代人がこの映画に「共感しづらい」と思ってしまうのも、ある意味当然なんです。
むしろ、そうあるべきなのです。
男女同権はさらに進んでいるはずだし、
夫の妻に対する態度も改められているべきです。
この映画に「共感」する男性は、減っていなければいけないのです。
この映画が、一人の男の人生を描いた名作であることは変わりません。
それは同時に、古い時代を生きた男の記念碑であり、
あるいは墓標なのかもしれません。



















































